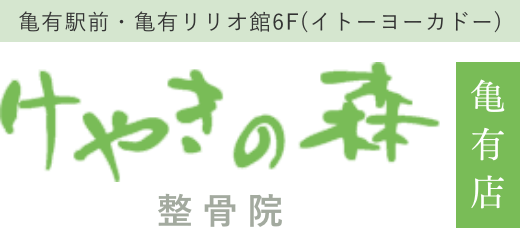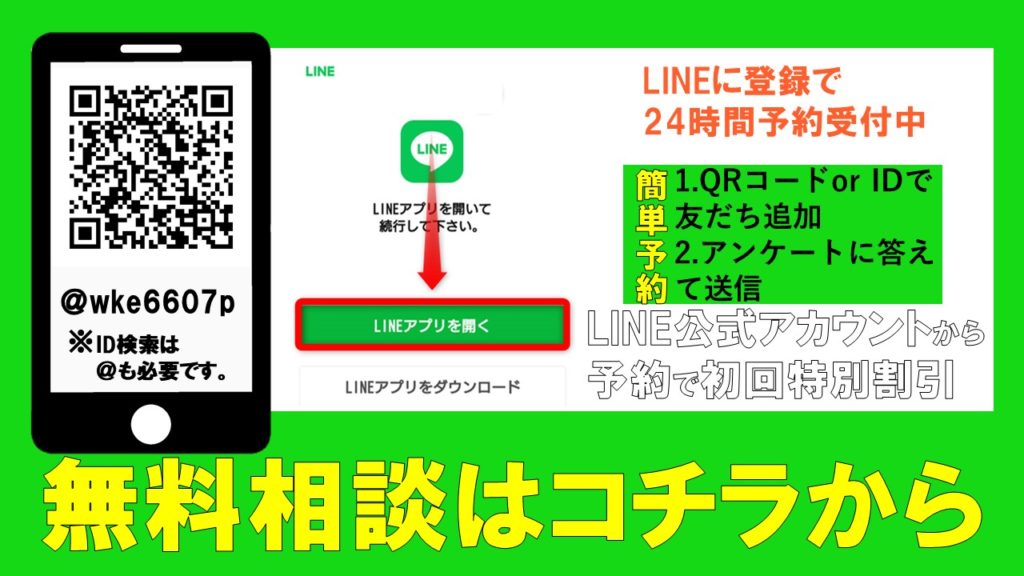ブログ
足の痛み
足首の捻挫とは?早く治す為の3つの方法と対処法について

日々の生活の中で足を挫いてしまった事はありますか?足首の捻挫は怪我の中では比較的起こりやすく、場所を選ばずに歩いて行動する以上は避けられない外傷の一つですね。足首は可動域が広く、歩く、走る、しゃがむなど多くの動作をするので、そのため問題が起こりやすいです。
足の捻挫は山道や段差の多い地形で高確率で起こり、筋肉の衰えや関節の硬さも原因の一つと言われています。スポーツを活発に行う学生が最も捻挫の頻度が高いと言われていますが、年齢層で言えば、どの年代でも足の捻挫は起こりやすいです。
今回のブログでは、もし足を挫いてしまった時にいかに早く治す事が出来るかについて3つの方法を解説して行きます!
足首の捻挫について

足の関節は人体の中で最も体重の影響を受ける部分で、直立した状態で掛かる負荷は全体重の50%と言われています。体重の約半分が足首に掛かっている状態で、歩いたり、走ったりするとそれ以上に負荷が掛かります。
足首の捻挫は、高低差のある地形で特に起こりやすいです。登山は勿論のこと、自宅にいても階段や玄関などちょっとした段差で躓いて転ぶというケースが多いのでは無いでしょうか?足の関節は体重を支えて衝撃を分散するような構造をしていて、筋肉や腱だけでなく骨と骨を固定する役割を持つ靭帯が多数あります。
前距腓靭帯
足首の捻挫で一番痛めやすい靭帯と言われていて、足の関節が過度に内側や下側に向かないよう固定しています。足関節の内反捻挫で最も起こりやすく、段差に躓いた時に足が引っ掛かって断裂してしまう場合があります。
三角靭帯
足首の内くるぶしから三角形を描くように関節を固定している靭帯で、テニスの切り替えし動作やスキーでの転倒事故で最も痛めやすい靭帯になります。前距腓靭帯ほど痛めることはあまり無いですが、無理な動きを制御するために必要な靭帯と言えます。
二分靭帯
足の基部(足先よりも踵寄り)の骨を繋ぐように固定している靭帯で、前距腓靭帯と場所が少し近い事から間違えられやすいのが特徴です。足が内返しに挫いてしまった時に自分の体重が掛かって痛めてしまうケースが考えられます。
捻挫では骨と骨を繋いでいる靭帯を損傷する事が多く、痛みや出血を伴うことがほとんどで、歩くときに不便を感じやすいです。生活する上では歩くことが普通なので、治りも遅くなりがちで仕事や家事に支障をきたしやすいと思います。
足の捻挫の場合、損傷度合いにもよりますが2週間から長くても1~2ヵ月は痛みや歩きづらさを感じる事があります。そんなに長い間、不便な生活を送らない為にも足の捻挫は、早く治すための3つの方法があるのです。
足首の捻挫を早く治す3つの方法
①足首の固定を優先する
捻挫の応急処置で優先的に行われているのが”RICE処置”と言われています。
R(Rest)安静・・・運動をしていた場合は直ちに中断して、患部を安静にすることで出血や損傷の広がりを防ぎます。
I(Icing)冷却・・・痛めた患部を冷やすことで、痛覚を麻痺させるだけでなく炎症の悪化を抑えられる。
C(Compression)圧迫・・・痛めた患部の周囲をテーピングや包帯で圧迫することで、炎症が広がることを防ぎます。
E(Elevation)挙上・・・患部を心臓よりも高い位置にすることで炎症を起こす元となる血流を一時的に低下させます。
これら全ては出来るだけ早い段階で行うのが得策で、足首をいかに動かさないか、適切な処置が出来るかがカギですね!
②痛めた足首に体重を掛けないようにする
捻挫に限ったことではないですが、痛めてしまった患部を早めに治すためには、いかに負担を掛けないかが大事です。
先ほど説明したRICE処置の安静に当てはまりますが、基本は使わないようにするのが早く治すための近道です。もし、スポーツの試合や大事な仕事で動かざるをえないときは固定はしたままで靴底に負担を和らげるソールを敷くのが良いと思います。
③周囲の筋肉を鍛える
足の捻挫は骨を繋ぐ靭帯が損傷しやすく、足のバランスを崩してしまうことがあるので基本は安静です。しかし痛めてから1~2週間ほど経てば症状も軽減してくるので、患部は無理に動かさずふくらはぎの筋トレや足指の運動を中心に行うことで血流を良くして修復を早めることが出来ます。痛めた直後に筋トレや運動を行ってしまうと炎症が起こるため、余計に時間がかかってしまうのです。
まとめ
足首の捻挫は日常生活を送る上ではリスクとして避けられない場合があります。歩いて行動する以上は足を挫いてしまうこともあると思いますが、そこでいかに適切な処置が出来るかが大切です!早く治すというのは人間も動物である以上、限界がありますが方法によっては驚くくらいに修復を早めることが出来ますので、是非参考にしてみて下さいね。