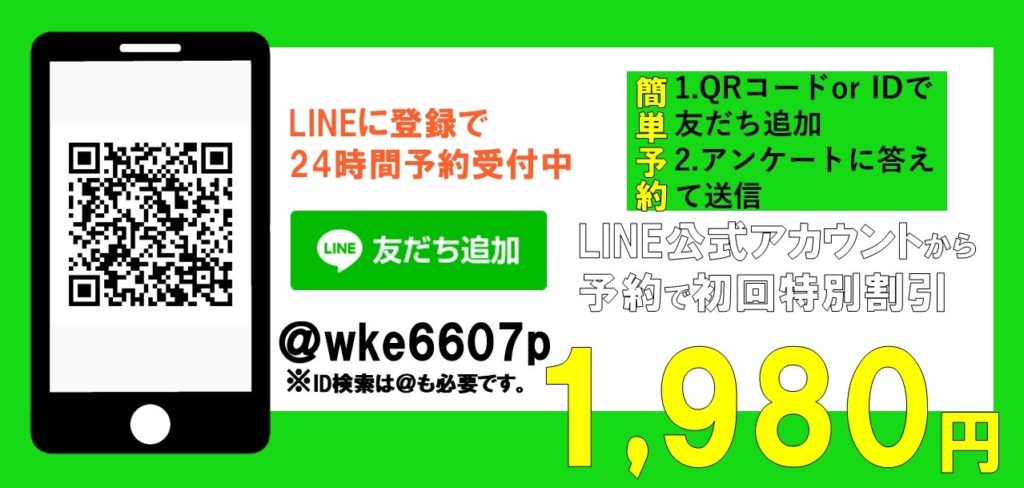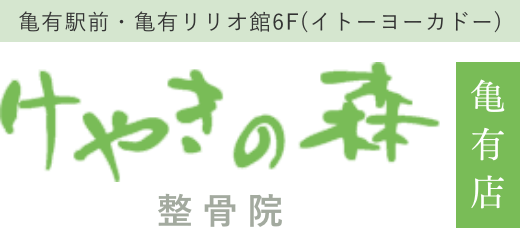ブログ
首の痛み
寝違え
治らない首の寝違えは何が考えられるの?

「痛みが全く引かない。」「首が痛くて動かすことが出来ない。」というような症状が続く場合は、本当に寝違えなのか疑うべきだと思います。今回の記事では、治らない首の寝違えは何が考えられるのかを解説していきます!寝違えを頻繁に起こしてしまう方や痛みや運動制限が続く方にこそ見て頂きたい内容となります。
寝違えの治癒基準は受傷してから約1週間ほど
首の寝違えは痛みを覚えてから数時間から2〜3日ほどで和らいでくると言われています。筋肉や関節に炎症が起こるため、痛みによって首を動かしづらくなってしまい、日常生活に大きな支障を引き起こすことがあります。炎症反応はほとんどの場合は2〜3日で治りますので、固まってしまった首が元に動けるようになる事を考えると約1週間と言えるのです。
寝違えは一度起きてしまうと再発しやすい
これは寝違えに限ったことでは無いのですが、一度完治したと思っても忘れた頃にまた再発してしまう場合があります。これはどうしてかと言うと、寝違えを引き起こしている根本的な問題が解決していないからなのです!これからこの記事の本題に入りますが、寝違えは起こるべくして起きていると言うのをまず知ってほしいです。
治らない首の寝違えは何が考えられるの?

頚椎椎間板ヘルニア
ヘルニアという言葉は腰で良く聞きますが、実際は首にも同様に起こりやすい疾患です。椎間板は背骨を構成している椎骨の間にある軟部組織で、背骨に掛かる負担を減らすクッション材の役割を果たしています。首にも椎間板はあるのですが、腰のヘルニアと違って不良姿勢による原因がほとんどです。ストレートネックや猫背などの不良姿勢によって椎間板が圧迫を受けて脊髄側に押し出されることで、腕や手先までの痛みや痺れが出現するのですが、寝違えだと思っていたのが実は頚椎ヘルニアだったというケースもあるようです。
頚椎症性神経根症
頚椎症性神経根症とは、加齢などで背骨を構成する椎骨自体の変形が起こり脊髄を圧迫することで生じる疾患です。ヘルニアと異なることは椎間板では無く骨自体に問題が起こってしまうので、根本的な治療が手術のみになってしまう点です。しかし、手術をして解決するという選択肢があるだけで実際に行うことは少ないようです。これは手術によるリスクもそうですが、痛みや痺れの症状が重篤で生活に支障がでてしまうレベルでない限りは改善の余地があるからです。寝違えと間違われやすいのは痛みだけの症状であり、痺れが出現している場合はこの疾患も疑うべきですね。
脊髄腫瘍
脊髄腫瘍は文字通り脊髄自体に腫瘍が出来る事で、大きく分けると硬膜外と硬膜内(硬膜は脊髄自体を包む保護膜のようなもの)に分類されています。硬膜は脊髄を保護する役割を持っていますが、この部分に腫瘍が出来てしまう事で脊髄を圧迫し首から肩の痛み、腕までの痺れが生じます。場合によっては吐き気やだるさ、頭痛などの症状も現れる事があります。神経症状を伴うものは寝違えと言えませんが、様々な疾患が考えられるため脊髄腫瘍もご紹介させて頂きました。
強直性脊椎炎
強直性脊椎炎は若年者に多く、頚部痛や腰痛、仙腸関節痛や殿部痛(坐骨神経痛)、胸部痛(肋間神経痛)、時に股関節~足関節などの痛みや腫れで発症します。痛む場所は移動することが多く、安静にしているより体を動かした方が軽くなるのが特徴です。重症例では初発から10~20年経過すると脊椎が動かなくなり、日常生活や就労に不自由を感じるようになってしまう事があります。炎症を引き起こすという意味合いでは寝違えと変わりありませんが、問題は首だけでなく他の部位の関節にも同様の症状があるかどうかです。寝違えと間違えるはずが無いと断定は出来ませんので、注意が必要な疾患です。
関節リウマチ
関節リウマチとは、免疫の異常により関節に炎症が起こり、関節の痛みや腫れが生じる病気です。進行すると、関節の変形や機能障害を来たします。原因は不明ですが、遺伝的要因や、喫煙、歯周病などが関係あると言われています。有名なのは手指や手首ですが、首を形成している背骨部分も関節があるため一概に起こらないとは限りません。寝違えとは明らかに関係なさそうですが、無意識の状態で首を痛めるのが寝違えのため原因が分かりづらいという事でご紹介しました。関節リウマチは血液検査による診断が主ですので、病院での診察が一般的です。
まとめ
寝違えとは言え、判断を誤ると危険な疾患が多くあります。ほとんどの疾患は医療機関で検査を受ける事で判明しますが、痛みが引いてしまうと病院に行かずに済ませてしまう人は多いです。確かにその通りなのですが、今回書いた寝違えの特徴から明らかにおかしいと思える点があった場合はすぐに診察を受ける事をお勧めします。