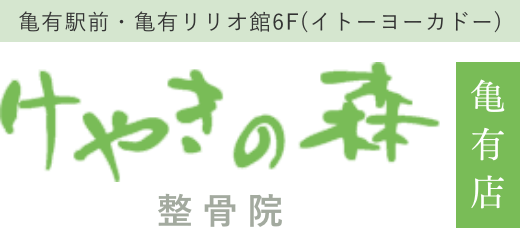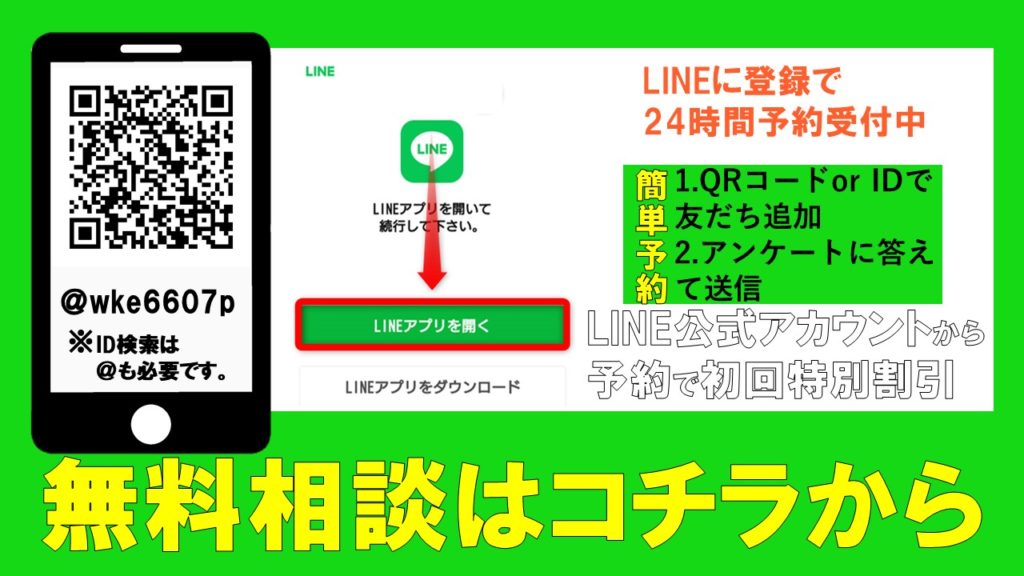ブログ
その他
鍼治療の危険性と副作用について|受けるべきではない13の症状

『鍼治療を受けたいけど、副作用や危険性が心配』
『どんな状態の時に受けたら良くないのかを事前に知っておきたい』
この記事では鍼治療を受けようと思っているけれど事前に下調べしておきたいあなたに向けて書きました。
鍼治療の危険性と副作用

公益社団法人 全日本鍼灸学会 学術研究部 安全性委員会による『鍼灸の安全対策』で行なった前向き調査によると14,039回の鍼治療のうち有害現象が発生した件は847件(0.03%)という報告があります。内訳は以下の通りです。
- 皮下出血・血腫370件(2.64%)
- 不快感109件(0.78%)
- 刺鍼部の残存痛94件(0.67%)
- 刺鍼時の痛み78件(0.56%)
- 出血74件(0.53%)
- 症状の悪化28件(0.20%)
- 不明26件(0.10%)
- 火傷24件(0.47%)
- その他19件(0.15%)
- 皮膚炎・皮下組織炎12件(0.09%)
- はりの抜き忘れ13件(0.09%)
このような報告がありますがほとんどの場合は軽症で一過性のものとなります。鍼治療の副作用として代表的な気胸や感染症といった重篤な事例は報告されなかったとされています。
また、厚生労働省『統合医療情報発信サイト』の鍼治療の安全性と副作用の科学的根拠によるとこのようなことが書かれています。以下引用:
鍼治療による合併症はほとんど報告されていません。しかし殺菌していない針の使用や、不適切な治療があると合併症がおこっています。
治療が不適切である場合、鍼治療により感染症、臓器穿刺、肺の虚脱、中枢神経系損傷などの重篤な副作用を引き起こします。
つまり、適切な鍼の使用や治療法であれば重篤な副作用を引き起こしたり合併症を起こすことはほとんどないということです。
現代ではディスポ鍼と呼ばれる滅菌消毒を行った使い捨てタイプの鍼を使用して行います。
受けるべきでは無い13の症状

WHO世界保健機関によると以下のような場合は受けるべきではない(禁忌)とされています。
- ・妊娠
- ・救急事態または手術を要する場合
- ・悪性腫瘍
- ・出血性の疾患
となっています。
妊娠

鍼の刺激によって陣痛を誘発してしまう可能性があるため、妊娠中に用いるべきではないとされていますが、不妊治療や腰痛といった目的で治療が必要な場合には充分注意が必要です。
逆を言えば陣痛を促進する為に行う場合や出産時間を短縮させるためには効果的です。一般的には妊娠3ヶ月以内であれば下腹部・腰仙部の刺鍼は禁忌とされています。妊娠3ヶ月以降の場合は上腹部や腰仙部が禁忌となっていますが、強い刺激を与えるような鍼治療は避けた方が良さそうです。
救急事態または手術を必要とする場合

鍼治療は救急事態を要する場合には用いるべきではありません。大至急救急病院に患者さんを送る必要があるのでしっかりとした応急処置を行う必要があります。なので外科手術の代用として鍼治療を行うべきではないのです。
悪性腫瘍
悪性腫瘍とは癌(ガン)のことです。特に腫瘍への刺激は避けるべきであるとされています。ただし、鍼治療の場合は患者の生活の質(QOL:クオリティーオブライフ)を高めるために痛みの緩和や化学療法や放射線療法による副作用の軽減などにも用いられるため、補助的な役割で行なう場合には有効的かもしれません。
出血性の疾患
凝血性の疾患(血友病やビタミンK欠乏症)または抗凝血治療中・抗凝血剤使用中(血液をサラサラにする薬)の患者には用いるべきではないと書かれています。
以上の事が鍼の禁忌となっているのですが、中にはForbes Japanの『絶対に受けてはいけない10のはり治療』には次のような場合も避けた方がいいという報告もあります。
- ・子宮類線維腫
- ・過敏性腸症候群
- ・滲出性中耳炎
- ・男性における下部尿路の症状
- ・高ピリルビン血症
- ・手根管症候群
- ・うつ病
- ・変形性関節症
- ・ベル麻痺(顔面神経麻痺)
は受けてはいけないという記事を発行しています。
子宮類線維腫
子宮筋腫、子宮平滑筋腫、子宮繊維筋腫としても知られている非癌性腫瘍のことで症状としては多量の出血、月経痛、下腹部の圧迫感、不妊、流産などがあります。
過敏性腸症候群
過敏性腸症候群の場合は省庁や大腸に異常が見つからないにも関わらず、便通の異常や腹部の不快感といった症状が続く病気の事です。過敏性腸症候群男場合は以下のような症状も出ます。
- 下痢や便秘が長く続く
- 下痢と便秘を交互に繰り返す
- 頻繁に腹痛が現れる
- 腹部膨満感
- 腹部がゴロゴロ鳴っている
- 排便すると腹痛や腹部の不快感が軽減する
- よくおならが出る
- 良くげっぷが出る
- 食欲がない
- 吐き気や嘔吐
滲出性中耳炎
鼓膜よりも奥にある『中耳腔』という空間に液体が溜まる中耳炎のことです。通常の中耳炎の場合は激しい痛みや熱を発することが多いのですが、滲出性中耳炎では激しい痛みや熱も伴わないことがあります。
男性における下部尿路の症状
主に前立腺肥大症が多いのですが以下のような病態や疾患でも起こります。
前立腺炎、前立腺がん
膀胱炎、間質性膀胱炎、膀胱がん、膀胱結石、膀胱憩室、過活動膀胱、低活動膀胱
尿道炎、尿道狭窄、尿道憩室
脳障害、認知症、パーキンソン病、多系統萎縮症、正常圧水頭症、進行性核上性麻痺、大脳白質病変
脊髄損傷、多発性硬化症、脊髄腫瘍、脊椎変性疾患(脊柱管狭窄症、椎間板ヘルニア)、脊髄血管障害、二分脊椎
糖尿病、骨盤内手術後
日本泌尿器科学会『男性株尿路症状・前立腺肥大症診療ガイドライン』より
高ピリルビン血症
血液の中に含まれる赤血球の分解によって生じる色素の事で、肝臓や胆道といった臓器に異常があるとピリルビンの数値が上昇します。特徴として『黄疸:おうだん』が見られ皮膚や眼が黄色く変色する症状が現れます。
手根管症候群

手根管とは、手首の部分にある骨と靭帯に囲まれた空間の事を言いますが、この空間には腱と神経(正中神経)が通ります。この正中神経が何らかの原因によって圧迫が加わったり擦れたりすることによって手の痺れ感や痛みを発します。
うつ病
ストレス(精神的・身体的)が重なることで、脳の機能障害が起きている状態の事を言います。脳がしっかり機能しないので考え方が否定的になったりします。以下のような症状があればうつ病のサインかもしれません。
- 気分が重い、憂鬱
- 何をしても楽しくない、興味が湧かない
- 疲労しているのに眠れない、一日中眠い
- イライラして気持ちが落ち着かない
- 自分を責めて自分には価値が無いと感じてしまう
- 思考能力が停止する
- 死にたくなる
変形性関節症
関節の周りに腫れや引っかかり感、違和感などが現れるものです。特に50歳以上の1000万人の方が変形性膝関節症による膝痛を経験していることもわかっています。その他股関節や肘関節にも症状を引き起こしてきます。
ベル麻痺(顔面神経麻痺)
顔面神経麻痺によって顔の筋肉(表情筋など)がコントロールできなくなった状態の事を言います。主に顔面神経麻痺の場合は脳腫瘍や脳卒中といった病気で起こりますが、はっきりとした原因が特定できない場合はベル麻痺と呼ばれています。
鍼治療の危険性と副作用について:まとめ
鍼治療は正しい方法で行なう場合には危険性が高まることや副作用の頻度も高くなることは稀です。院内に手指を消毒する為のものは整っているのか?鍼は使い捨てタイプを使用しているのか?鍼の免許を取得してどれくらい経過して、どのくらいの患者さんを治療してきたのか?この辺を踏まえて鍼治療を受ける場所を選んでみてはいかがでしょうか?